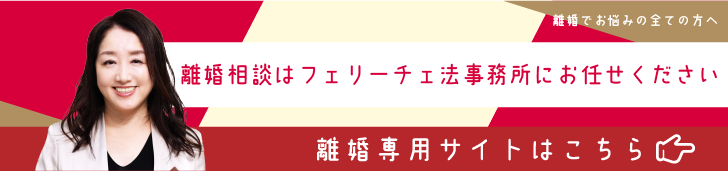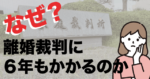2020年4月に民放が改正され、「配偶者居住権」というものが認められるようになりました。しかし、「配偶居住権」と聞いても何のことなのか、どんな権利なのか分からないという人もいるでしょう。
今回は配偶者居住権についてご紹介します。
配偶者居住権が設けられた背景
高齢化が進む日本で、被相続人の配偶者は被相続人が亡くなってからも長期にわたって生活することは珍しくありません。この場合、配偶者に住み慣れた居住環境を確保しつつ、生活資金をとしての貯金を一定程度は確保したいという希望を有する人は多いです。
従来の法律では残されたが配偶者が自宅に住むためには、「遺産分割において配偶者が自宅の所有権を確保する」、「居住権と所有権を取得した人との間に賃貸契約を結ぶ」という方法があります。
しかし、この方法では建物の評価額の高騰で貯金を確保することが難しくなったり、賃貸契約ができなければ居住権が確保で気なかったりするという問題がありました。
この問題を解決し、残された配偶者の居住建物と生活資金の安定化を図ることを目的として配偶者居住権が設けられました。
配偶者居住権とは?
普段から法律に触れていない人にとっては「配偶者居住権」と言われても、何のことだか分からないという人もいるはずです。
配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者が自宅の権利を相続しなくても住み続けていい」という権利です。
1:配偶者が権利を相続しなくても住める
配偶者が自宅の権利を相続するなら、誰に文句を言われることなく自宅に住む続けることができます。
しかし、配偶者が権利を相続しなかった場合には、権利を相続した人から自宅を追い出されるという可能性もゼロではありません。配偶者居住権とはこの可能性をなくすもので、権利を相続しなくてその自宅に住む続ける権利だけは保証されるというものです。
そのため、自宅には「所有権」と「住む権利」という二つの権利があることになります。
2:住んでいる配偶者のみに認められる
配偶者居住権は相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にのみ認められる権利で、配偶者所有権の登記が必要です。
「相続が発生した時点で住んでいる」という条件があるため、仮に配偶者が別居している場合はこの権利は認められません。また、配偶者居住権は不動産登記簿謄本に登記しなければ効果を発揮しません。
そのため、相続が発生した時点で登記する必要があります。
3:配偶者居住権は売却や相続できない
配偶者居住権は売却や相続をすることができず、配偶者が死亡することによって消滅します。
この権利はあくまで配偶者のみに認められた権利なので、配偶者以外の人に売却することができません。
配偶者居住権を持って居る人と、自宅の所有権を持っている人が違う場合、配偶者所有権を持っている人が死亡し、権利が消滅した時点で、所有者に全ての権利が移ることになります。
4:自宅にのみ効果を発揮する
配偶者居住権の注意点として配偶者居住権の効果が発揮されるのは自宅のみということです。
つまり、自宅が建っている土地には効果が発揮されません。そのため、土地の所有権が配偶者ではない場合、土地を売られてしまうと自宅を出なければならないということになります。
土地は効果の範囲外ということを踏まえた相続を行う必要があります。
5:再婚でも効果を発揮する
高齢者となり熟年再婚したなどという場合、遺言を残しておくことによって再婚した配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。
配偶者居住権を設定する際の注意点
配偶者居住権には設定するためには、被相続人が遺言書などで「配偶者に権利を取得させる」ということを記載するか、相続人の分割協議で決めて登記を行う必要があります。
遺言書で配偶者居住権を配偶者に取得させる際には「相続」ではなく「遺贈」という言葉を使わなければなりません。
「相続」と「遺贈」には大きな違いがあり、「遺贈」の場合は配偶者が配偶者居住権を欲しくないと考えた時に、この権利だけを放棄することができます。
しかし、「相続」という言葉を使ってしまうと一部を放棄することはできず、放棄する際には「相続放棄」をするしかなくなくなってしまいます。
遺言などでは相続という言葉を使いがちですが、配偶者居住権については注意しておきましょう。
配偶者居住権は離婚した配偶者には有効か
離婚をした人は配偶者ではなく、「元配偶者」という扱いになり、配偶者居住関係ありません。離婚をしている時点で配偶者居住権だけではなく、相続の権利もなくなります。
しかし、離婚した元配偶者との間に子供がいる場合は、この子供には相続の権利があります。
まとめ
配偶者居住権についてご紹介してきました。
相続後も自宅に住むことはできますが、相続時に自宅に住んでいる人でなければいけない、登記をしないと効果を発揮しないなど、難しい面も多くあります。
自分ですることが難しい場合は弁護士に相談することでスムーズに問題を解決できるでしょう。